COLUMN
[不動産コラム]
金利上昇中!今、住宅ローンを選ぶなら?

出典:シルバーブレット / PIXTA(ピクスタ)
近年、社会がインフレ傾向に転じ、さまざまな物価が値上がりしています。住宅ローンの金利も上昇傾向にあります。現在、固定金利よりも金利が低い変動金利を選ぶ方が多くなっていますが、金利が上昇するとどれくらい負担額が増えるのでしょうか。変動金利が上昇したときにどのように手当てをするべきか、考えてみました。
固定金利とは? 変動金利とは? どう違う?
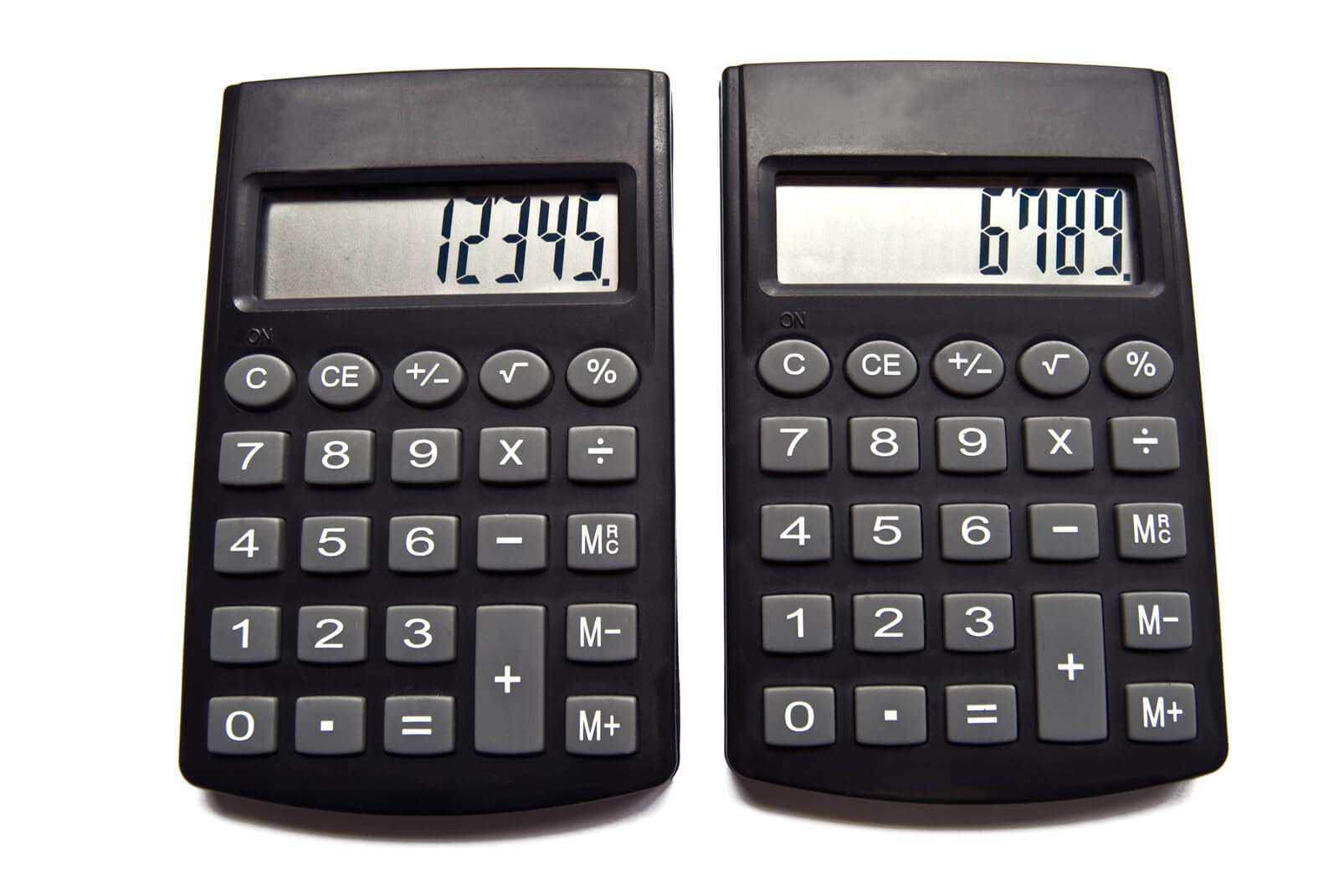
出典:Perutskyi Petro / PIXTA(ピクスタ)
最初に「固定金利」と「変動金利」の違いを知っておきましょう。
「固定金利」とは、定められた期間、金利が上昇しても毎月返済額が変わらないものです。固定期間には、3年程度の短期から10年程度の中期のもの、35年など返済が終了するまでのものなどがあります。固定期間が終わると、変動金利に自動的に切り替わるものや、再び固定期間を選択できるものなど、金融機関によってさまざまな商品があります。
固定金利のメリットは、固定金利期間中の毎月返済額が固定されるため、資金計画が立てやすいこと、金利上昇が起きても「毎月返済額が増えてしまう」と、神経をすり減らすことがないことでしょう。デメリットは、変動金利より金利が高いので、変動金利が固定金利より低い状態が続くと、総返済額が増えてしまうことです。
なお、金利が上昇傾向にあるときは、まず固定金利が上がり、その後に変動金利が上昇するという構造になっています。
一方、変動金利とは、借入期間中に金利の変動があれば、毎月返済額が変わるものです。
ここで、金利は半年に一度、見直されます。ただし、実際の返済額は5年ごとに見直す方法を採用する金融機関が多くなっています。一部に金利上昇の翌月から返済額が変わる商品を販売している金融機関もありますが、限定的です。
また、金利がどんどん上がっていったとしても、毎月の返済額は見直し前の1.25倍以上になることはありません。例えば、毎月返済額が10万円の場合、金利が上昇しても支払額は12万5000円が上限となります。
変動金利は、短期プライムレート(短プラ)という金利に影響を受けます。短プラとは、金融機関が企業に融資を行う際の基準金利のこと。一般的には1年未満の短期の貸し出しに適用される金利です。短期プラは、日本銀行の政策金利に影響を受けています。各金融機関がこの日銀の政策金利を元に独自に設定しています。
長らく変動金利は上がりませんでしたが、最近では、日本銀行の政策金利は上昇傾向にあります。このため、変動金利を選ぶ場合、日銀の動向に意識を向けておきたいものです。
変動金利は、現時点では、固定金利よりも低く設定されているため、大幅な金利上昇がなければ、総返済額が固定金利よりも少なく済む可能性がある点がメリットです。一方で、金利の上昇が続くと、毎月返済額は1.25倍に抑えられたとしても、元本がなかなか減らず、返済総額が増えてしまいます。また、いつまでたっても返済が終わらず、予定の借入期間が来ても返済をし続けなければならない可能性がある点や、家計にかかる住宅費の割合を予想できない点がデメリットです。
どの金利を選ぶのがいい?

出典:bonkura2002 / PIXTA(ピクスタ)
では、固定金利と変動金利、自分たちにとってどちらを選ぶのが良いのでしょうか。
その前に他の人はどう考えているかをみておきましょう。
民間金融機関と提携して「フラット35」を提供する住宅金融支援機構が、2025年1月に公表した「住宅ローン利用者の実態調査」によると、金利について「現状よりも上昇する」と回答した人が62.9%(2024年4月調査比 +12.4%)になっています。また、利用した住宅ローンの金利タイプは、「変動型」を選んだ人が77.4%(2024年4月調査比+0.5%)に上っています。日本銀行の金融政策変更の影響については、「住宅ローン選択」に関しては、39.1%が「変化あり」と回答しています。
出典:https://www.jhf.go.jp/files/400372462.pdf
一方で、「住宅ローン利用予定者」への調査では、希望する住宅ローンの金利タイプ は、「変動型」が38.7%(2024年4月調査比 ▲1.4%)、「固定期間選択型」が33.3%(2024年4月調査比 ▲0.3%)、「全期間固定型」28.0%(2024年4月調査比 +1.7%)と、全期間固定型がやや増えています。日本銀行の金融政策変更が、「住宅取得計画」に関して「変化あり」と回答したのが58.2%、「住宅ローン選択」に関して「変化あり」62.5%という回答になっています。
出典:https://www.jhf.go.jp/files/400372464.pdf
このようにみてくると、金利が上昇傾向にあるとはいえ、やはり現時点では、変動金利を選んでいる人、これから借りる予定のある人でも変動金利を選ぼうという人が最も多いことがわかります。
ここで注意したいのは、変動金利を選ぶなら、金利上昇を視野に入れ、対応できるように十分な返済計画を立てておくことです。
変動金利が上がると返済額はどう変わる?

出典:masamimix / PIXTA(ピクスタ)
では、金利の上昇によって、いくら上がるのかを試算してみましょう。
たとえば、
・3000万円を35年返済の元利均等返済で借り入れするとき。
当初5年間の金利が0.5%としたら、
そのときの毎月返済額は、77,875円
5年目に0.7%にアップすると、
毎月返済額は、80,180円となり、毎月2305円増になります。
10年目に1.0%にアップすると、
毎月返済額は、82,561円となり、借入当初より4686円、
5年前より毎月2381円増えます。
また、当初5年間0.5%で毎月返済額は77,875円、
5年目に1.0%にアップすると、
毎月返済額は 83,719円となり、毎月5844円、負担が増えます。
10年目に1.5%にアップすると
毎月返済額は、87,842円となり、借入当初より9967円増、
5年前より4123円の負担増となります。
毎月の金額をみると、金利の上昇はそれほど負担には思わないかもしれませんが、
お子さんが成長すると教育費がかかります。また家族のレジャー費用や帰省費用などの負担も増えるでしょう。昨今はインフレ傾向にありますし、できるだけ予定外の出費は減らしたいものではないでしょうか。
そこで、変動金利を選ぶ場合は、ぎりぎりで試算するのではなく、ある程度、余裕をもっておきましょう。
たとえば、金利を2~3%程度で試算をして、仮に変動金利が3%程度まで上昇したとしても返済できるくらいの貯蓄しておくことです。
仮に、上記と同じ条件で、固定金利で35年間、借りた場合、
金利が2%なら、毎月返済額は、9万9378円。変動金利との差は、2万1503円。
金利が3%なら毎月返済額は、11万5455円で、
変動金利との差は、3万7580円。
これを貯蓄しておくと、いざというときの繰り上げ返済に充てられます。金利が上昇しなければ別の使い道に充てられるでしょう。
いかがでしょうか。この金額を負担に思うかどうかが、変動金利を選ぶかどうかのポイントです。
ここで、繰り上げ返済について簡単にご説明します。金利が上昇しても、繰り上げ返済をすることによって、利息を減らすことができ、金利上昇によって増えた負担分を無くすことができます。
繰り上げ返済には、返済期間を短くする「期間短縮型」と、毎月返済額を増やさないようにする「返済額軽減型」があります。このうち、「期間短縮型」のほうが、総返済額を減らすことにつながりますが、これによって、住宅ローン控除の適用が外れてしまうことがあるので、金利が上昇したときに慌てて繰り上げ返済をするのは避けておきたいところです。

